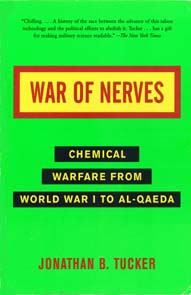(訳者あとがきから)
本書でジョナサン・タッカー博士が描くのは、神経剤という最強の化学兵器の偶然による発見からその工業規模での製造、局地的な紛争での使用からイラン-イラク戦争での大量使用を経てテロリストへの拡散、そして今度は、これまで開発と備蓄に傾注していた膨大な努力と予算を逆向きに注いで、国際社会の合意の下にこれを大量廃棄していく、という歴史である。それはまた、第二次世界大戦における枢軸国と連合国との対立から米ソを軸とした冷戦構造への変化を受け、大国が安全保障のための軍備に大量破壊兵器を組み込む一方、それが情勢不安定国を経てテロリストへ拡散する懸念から新たな戦争が起きているという世界情勢の大きな流れと一体の、しかしこれまで実証的に詳述されることのなかった歴史でもある。
冷戦構造が崩れると、敷居の低くなった化学兵器関係の技術や知識がテロリストにわたる懸念が高まり、それに対する準備を欠いた日本で実際に使用されるに至った。化学兵器の開発、製造、備蓄、移動及び使用を全面的に禁止する条約が発効して10年以上が経過した現在、大規模な戦争に化学兵器が使用される虞は遠ざかりつつある。一方、小規模であっても効果があることを認識したテロリストによる使用に対する恐怖は高まっている。
平和目的が一切存在しない殺傷兵器である神経剤兵器も、その開発過程では、通常の工業製品の開発と同様、あるいはそれ以上の研究努力が払われてきた。実験を行わないとその効果のほどが明らかでないことから、実験にも大量の神経剤が消費され、環境を汚染し、ときには人命までもが犠牲になった。そこには、無用な殺傷を防止するための兵器の開発は正当化できるという科学者の誤った倫理感と、自分たちが開発しなくても敵国は開発してしまうであろうという競争意識が存在した。効果的な防護のためには敵の攻撃手法の研究を行う必要がある、との論理から、自らの攻撃能力も高められた。